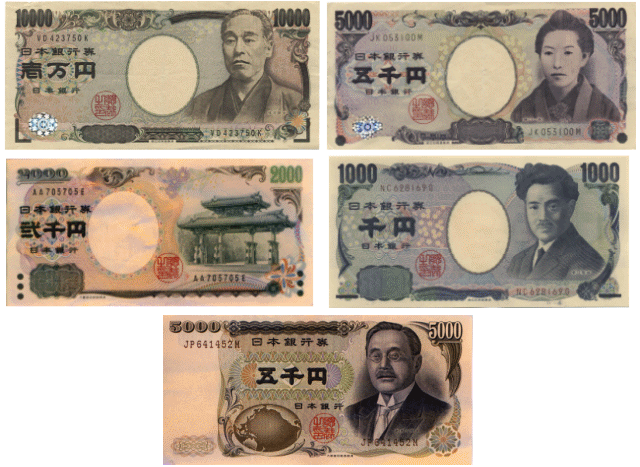|
紙幣は3種、一万円券、五千円券、千円券(二千円券は新札発券しません)でシリーズF券と呼びます。 「隠された紙幣の能力」らしく情報をかみ砕きます。 紙幣仕様 1.一万円券 肖像 渋沢栄一(大蔵省創設時の初代紙幣頭) 裏面 東京駅 76mm 160mm 2.五千円券 肖像 津田梅子(女子英学塾を創設) 裏面 フジ(藤) 76mm 156mm 3.千円券 肖像 北里柴三郎(北里研究所を創立) 裏面 富嶽三十六景 葛飾北斎「神奈川沖浪裏」 76mm 150mm すき入れ(すかし)の高精細化 一万円券及び五千円券にテープ状ホログラム 千円券はパッチタイプホログラム ホログラムは、肖像3D画像が回転する 記番号10桁 識別マーク 目の不自由な人向け 指の感触により識別できるマークの形状と配置変更  額面数字の大型化(表・裏) デザインとして最悪になってしまった。威厳ゼロ。このデザインでヨシと思った事、理解に苦しむ。 |