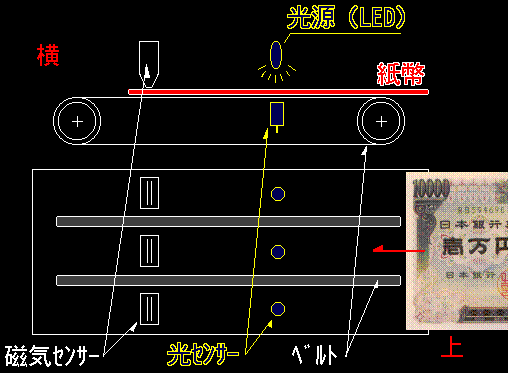
| シンプルで効果的な構造です。ご紹介する構造はあくまでも一例です。実際のセンサ数や位置はメーカやモデルにより異なります。 |
| 自動販売機や両替機で多様されている紙幣識別機の構造例をご紹介しましょう。 |
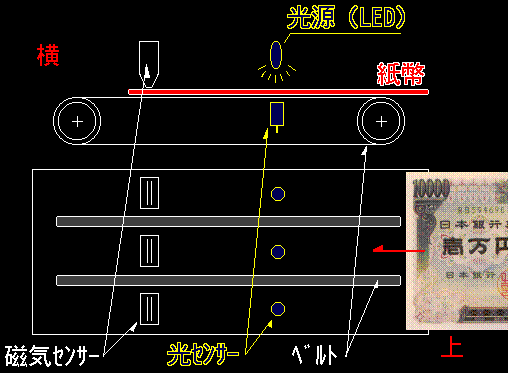
| シンプルで効果的な構造です。ご紹介する構造はあくまでも一例です。実際のセンサ数や位置はメーカやモデルにより異なります。 |
| ベルト駆動 |
| 大半が紙幣の搬送にベルトを採用しています。通常は下にベルト、上部はローラで押さえるタイプが多いようです。機種によっては、上下共にベルトを採用しているものがあります。過去に歯車の組み合わせゴムローラだけの搬送方式がありましたが、非常に音が大きくスピードに限界もあり、加えて紙幣の搬送中のあばれで正確なデータ採取に難がありました。 |
| 磁気センサ |
|
殆どのメーカが採用しているセンサです。インキに含まれている磁性体の有無/強弱を読み取ります。 その昔、犯罪者は白紙に8mmテープを貼っていたようです。現在では、数多くの磁気センサを取付け、場所の特定ができないような工夫がされています。 磁気センサーの数が増えることで、より一層の紙幣情報を取得することも可能となりました。メーカによっては、表裏4個所以上で磁気特性を見るものもあるようです。 |
| 光センサ |
|
波長として、可視光線と近赤外線センサーを採用するメーカが殆どです。可視光線は紙幣の印刷の濃淡を情報として判定しています。 光源には、電球やLEDを使用しています。上部より照射し透過された光を裏側にあるセンサで受取ります。図柄を電気信号に置き換えて紙幣情報とします。 透過式を採用するにはいくつかの理由がありますが、一番の目的は光の透過にで表裏の図柄情報が合成され一度で採取できる利点があります。透過式では、センサ数の節約も可能となります。 |