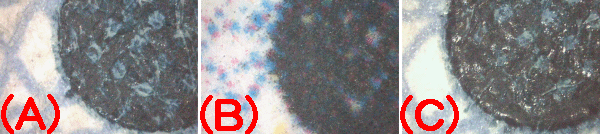
|
|
| 凹版 |
|
10元紙幣、表面右下にある盲人用識別マークが凹版です。指で触ればインクの盛り上がりを感じることができます。偽札は凹版印刷されていないために、一般の印刷やコピーのように感触はなくツルツルしています。 (A)両替不可: 下地の印刷の上に厚みのあるインクが見えます。凹版印刷の特徴と言って良いでしょう。 (B)偽札: カラーコピーやインクジェットプリンタで作られた偽札の特徴としてドットが見え凹版の特徴であるインクの厚みは見えません。間違いなく偽札です。 (C)本物: くっきりとしたインクの盛り上がりが見えます。 凹版印刷を模造することは困難だと言われていますが、(A)はインクの盛り上がりがあるにしてもその厚みは高くありません。劣化によるものと想像できますが、真贋判定は難しいでしょう。また、ここまで古くなると指で触っても凹版のざらつきは感じることが出来ません。怪しさが増すだけの判定要素となってしまいます。 |
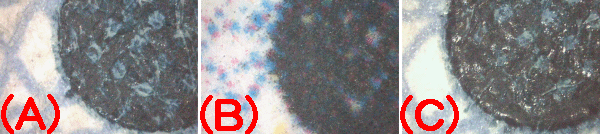
| 合わせマーク(古銭貨幣デザイン) |
|
発行時期で場所は異なりますが、表面左中央または表面左下側にある丸型のデザイン(古銭をモチーフにしたもの)、光にすかすことで表と裏のデザインが重なると古銭図案になります。 (A)両替不可: 面と裏の絵は綺麗に重なり円を形成しています。色も悪く紙質も悪化していますが判定としては真券に思えます。 (B)偽札: ズレは大きく、偽札ランクとしてもB級。なお、Sランクの偽札は本物の紙幣同様に表と裏のデザインは綺麗に重なるので、絶対的な真贋ポイントにはなりません。 (C)本物: 綺麗に円を形成しています。本物の要素として表と裏の印刷はあっています。 合わせマークは最近の技法ですが、すでにSランクの偽札では再現しています。(A)も(B)も本物の紙幣として考えてもいいように思えます。 |
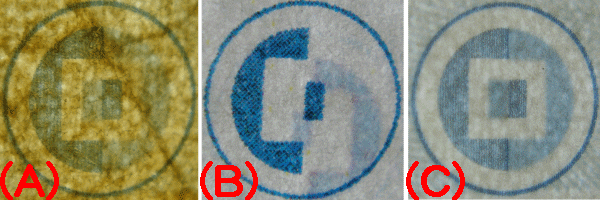
|
多くの真贋チェックポイントのある現在の紙幣ですが、あまりにも汚い紙幣だとその真偽を確認するに至らないことがわかります。銀行は(A)の紙幣を偽札と疑い日本円には両替しませんでした。実際に偽札であるかはわかりませんが、一定の条件はクリアしていると思われ本物であると考えていいと思っています。君子危うきに近寄らずが日本の銀行の判断なのでしょう。我々が自衛しない限り、銀行も国も何ら保証してくれないことを理解する必要があります。汚れのひどい紙幣は国内に持ち込まず中国内で換金するか使用するほうが良さそうです。 なお、過去の偽札情報から考え、金種のレベルでその偽札のランクも変わるようです。100元、50元は極めて精巧に作られている偽札が存在しています。また、10元や20元といった紙幣だとBランク程度のコピー品が出回っています。ルーペでマイクロ文字を確認すればすぐに判定できるものなので中国に旅行される方は事前に紙幣の特徴を押さえておくと良いでしょう。 |